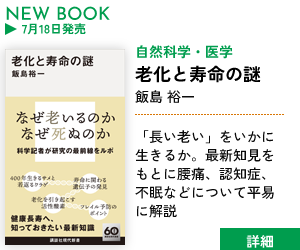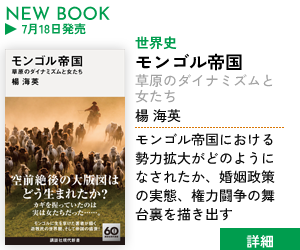意識とはなにか。なぜに、数千年もの長きにわたり、哲学者や科学者の間で喧々諤々の議論が繰り広げられているのか。なぜに、現代科学の最後のフロンティアと評されるのか。
同業の神経科学者の間にも、「意識は定義すらされていない」との誤解が蔓延する嘆かわしい現状があるが、意識は紛れもなく定義されている。わかっていないのは、その意識がなぜに脳に宿るかである。
そこで、この場を借りて、哲学者トマス・ネーゲルによる意識の定義“Something that it is like to be”を皮切りに、意識とその深淵なる謎について、これまでわたしが培ってきたものすべてを出し切って説明したい。
本文を読解する短い時間のなかで“悟り(意識の定義の理解とその謎の実感)”を開くことができるか、ぜひ挑戦してみてほしい。先人たちによる幾多の入門書がその指南に失敗してきたなか、大多数の人を導くことができたなら、著者冥利に尽きる。
「意識のアップロード」でアップロードしようとしているものは一体何なのか。アップロードを実現するために、何が解決されなければならないのか。「意識のアップロード」の具体的な手順に入る前に、はっきりさせておく必要がある。
前回記事はこちら『夢の「新型ブレイン・マシン・インターフェース」で意識を解き明かす』
ご愛読、誠にありがとうございました。
本連載(全8回)は、大幅加筆のうえ、再構成し、2024年6月、
『意識の脳科学――「デジタル不老不死」の扉を開く』(講談社現代新書)として刊行されました。
Something that it is like to be
前回の連載で、意識を“Something that it is like to be”「それになる感覚」と定義した。これをきちんと理解するにはある種の悟りが必要だが、あれから早数ヵ月、その意味するところはストンと腹落ちしたただろうか。
哲学者トーマス・ネーゲルによるこの定義は、一度わかってしまえば、言い得て妙の優れもので、短い言葉のなかにその本質をついたものだ。まさに、他に言い表しようのないくらいに。その一方で、「それになる」の日常的な言葉遣いから、様々な誤解を生みやすいことも確かなようだ。最近になって、そのことを思い知らされた。
この6月からわたしの担当する学部講義「脳神経科学」がはじまった。2018年の開講以来、どのタイミングで意識の定義を導入するか試行錯誤してきたが、今年度は、初回講義で挨拶代わりに “Something that it is like to be”を披露した。これまで培ってきたヒット率の高い解説を総動員して。
しかしながら、結果は惨敗。端からわかっている学生にはわかるが、初見の学生にはほとんど通じなかったようだ。最近開発したジェットストリームアタック(機動戦士ガンダムに登場する畳み掛け戦術:次節以降、さらなる改良版が登場)を携え、多少なりとも自信があったのだが、見事に打ち砕かれてしまった。
その苦境からどう立て直すべきか思案していたところ、まったく単位にならないのにもかかわらず、熱心に聴講してくれる学生さんたちと、昼食を食べにいくようになった。一人は医学部の一年生、もうひとりはなんと九州大学の一年生で、毎週、はるばる東京まで通ってきてくれている。
初回の講義から数週間経ったある日、二人のうちの一人が、「それになる感覚」の意味合いがおぼろげながらつかめてきたと打ち明けてくれた。解脱途中のリアルタイムサンプルの出現である。この好機を逃すまいと、いかにして悟りに至ったのかを問うてみた。すると、ネーゲルの「それになる感覚」について、当初、「誰から見たときの、“それになる”感覚なのか?」と考えあぐねていたのだという。
日常的にわたしたちは「誰々になったつもりで考えなさい」といった物言いをする。当然のことながら、そこには主語である「あなた」が隠れており、それが実際に意味するのは「“あなた自身が” 誰々になったつもりで考えなさい」である。
しかしながら、ネーゲルの「それになる感覚」には隠れた主語は存在しない。まさに、それ自身が「それになる感覚」を有するかを問うているのだ。
そのことを踏まえ、“Something that it is like to be”を意訳してみよう。「何かになったとして、そのときに何らかの感覚がわいたならば、それこそが意識である」としたなら、もうすこしわかりやすいだろうか。
仮に「なる」対象が石ころであれば、たとえそれになったとしても、何の感覚もわかないだろう。コップの中の水や旧式のラジオ然り。
その一方で、この瞬間、わたしの脳になったなら、間違いなく様々な感覚がわくことになる。今まさに、この文章をパソコンで打ちながらわたしが目にする黒の鮮やかなフォント、カタカタと耳に響き、指に伝わってくるキーボードの感触、煎れたてのコーヒーの香り。同じく、数週間後にこの記事を目にするであろうみなさんの脳になったなら、種々の感覚がわくことだろう。
誤解のないよう、ひとつことわっておきたい。ここで論じているのは、脳の情報処理ではない。情報処理を行っている最中の脳にわく、処理ごとの「それになる感覚」である。視覚情報処理をおこなっているときにわく「見える」、聴覚情報処理をおこなっているときにわく「聴こえる」といった感覚だ。
何も難しいことを言っているわけではない。「見える」であれば、顔の前にあるものは見えるし、頭の後ろは見えない。ただそれだけのことだ。「見える」や「聴こえる」といった言葉に、なにか特別な意味や仕掛けを含ませているわけではない。「部屋を明るくしたから見える」、「音量を上げたから聴こえる」といったように、あくまで、日常的な意味合いで用いているにすぎない。
専門家が、それが意識だとしつこく言うなら、それはそれで一旦認めるとして、おそらくみなさんの頭の中に渦巻いているのはこんなことだろう。なぜに、一見当たり前の「見える」や「聴こえる」が意識なのか。なぜに、そんなものを巡って、ギリシャ哲学以来、数千年もの長きにわたり喧々諤々の議論が繰り広げられているのか。
それらの疑問を紐解く鍵は、「見える」にしても、「聴こえる」にしても、わたしたちの脳になぜかわく「それになる感覚」であり、決して当たり前のものではないということだ。当たり前でないからこそ、哲学者や神経科学者の飯の種であり続けている。
さきほどの意訳に沿って言い換えるなら、脳になったとして(あなた自身は脳であるわけだが!)、そこに「それになる感覚」がわくからからこそ、わたしたちは「見たり」「聴いたり」することができるのだ。
「見える」や「聴こえる」の意味を日常的なものとして要石的に据え置いたうえで、なぜにそれらの感覚が、脳にわく「脳になる感覚」であるのか、なぜに、当たり前のものではないかについて思いを巡らしながら、次節以降、じっくりと読み進めてほしい。