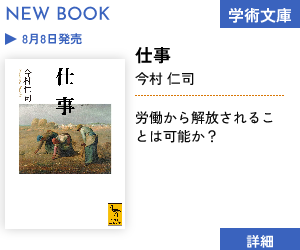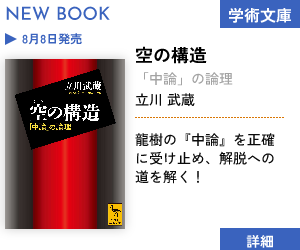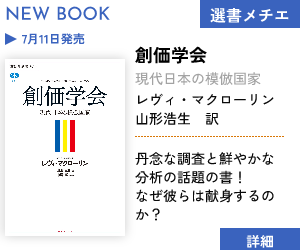2024.06.04
「物理帝国」のヘゲモニーを牽引した冷戦の力学 しかし「核のツケ」はいつ誰が払う?
アインシュタイン、オッペンハイマー、湯川秀樹……20世紀、あまたの巨星たちに導かれ、栄光の時代を謳歌した物理学は、その「帝国」の版図を科学・経済・社会のあらゆるシーンに拡げました。自身第一線で活躍してきた佐藤文隆氏が、帝国の「黄昏」も囁かれる時代の転換期に、物理学の栄光の歴史とあるべき未来を、縦横無尽に語ります。
今回はオッペンハイマーの失脚から冷戦期の物理学の隆盛、そして冷戦終結の後の世界まで。
(以下は氏の最新刊『物理学の世紀』からの抜粋です。)
今回はオッペンハイマーの失脚から冷戦期の物理学の隆盛、そして冷戦終結の後の世界まで。
(以下は氏の最新刊『物理学の世紀』からの抜粋です。)
核の帝国――オッペンハイマーの栄光と挫折
1945年、第二次大戦が終わり、オッペンハイマーは国民的英雄となり、科学力で国家に貢献した他の科学者もそのまま政府への有力な影響力を維持した。物理学者の一部は核エネルギーの国際管理を提案するなどの先見の明を発揮したが、戦後間もなく明確になった冷戦体制の中では、現実への深入りは同時に物理学者を次々と政治に巻き込むにいたった。
49年にソ連が原爆を保有し、米ソはさらに強力な水素爆弾の開発に向かった。54年には、ビキニ環礁実験で日本の漁船が被曝し、放射能「死の灰」への恐怖が大衆の前に姿を現わした。
 1946年7月、マーシャル諸島での核実験(GettyImages)
1946年7月、マーシャル諸島での核実験(GettyImages)
核独占が破られ、また中国に共産政権が成立した状況は、アメリカ国内に防共のパニック的雰囲気を生んだ。そうした中で、水爆開発に消極的な姿勢を見せたオッペンハイマーは、反共マッカーシー旋風(50~54年)の恰好の餌食にされた。
この科学界最高権力者の失権をめぐって、有力な物理学者が推進派と反対派に分かれて争い、気まずい傷跡をアメリカ物理学界に残した。
「愚行としての原爆」へ
原爆を人類を滅亡させる恐怖の装置と考えるようになったのは、戦後10年ほどしてからである。被曝の惨劇は厳然としてあったが、多くの人々にとっては、大戦で自ら経験した参戦や空襲の悲惨さの実感が情報による原爆の認識を上回っていた。さらに、日本に進駐した占領軍は巧みな検閲制度によって原爆の惨劇を社会から見えなくしていた。