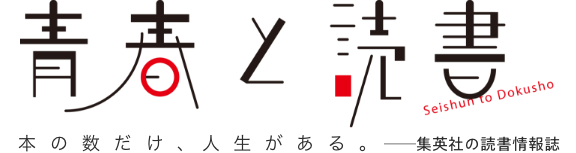[巻頭インタビュー]
一生に一度しか書けない、私にとって特別な作品になりました
抜群のキャラクター造形力と関係性が織りなすドラマ作り、そして「この状況でどんなことが起きたら一番面白く、一番意外か?」というシチュエーション・コメディ的発想の妙味が支持され、若手最注目作家となった佐原ひかりさん。最新刊『スターゲイザー』は、男性アイドルを題材にした全六編の連作集だ。自他ともに認める、「光」に満ちた作品となっている。
聞き手・構成=吉田大助/撮影=山口真由子

―― アイドルを題材にした小説は幾つも類例がありますが、どれも女性アイドルの話でした。男性アイドルグループを題材にした小説は、相当珍しいと思うんです。まだ誰も書いていない物語を……と探っていく中でこの題材に辿り着いたのでしょうか。
私は基本的に、次にどういう話を書くかは編集さんとおしゃべりしながら決めていくんです。今回も何が好きとか何にハマっているかという雑談をしていた時に、「小説すばる」の編集さんから宝塚歌劇団が好きというお話が出たので、私は男性アイドルが好きです、と。そこでブワーッとしゃべったら、「それだけ詳しいなら書いたほうがいいですよ!」と。なので題材選びの理由は、私が好きだった、というだけです(笑)。ただ、まだあまり書かれていないという意味では、プロデビューする前の、アイドル事務所の養成所の男の子たちの話にするのがいいんじゃないかな、という考えはありました。
―― それで、アイドル事務所・ユニバースに所属するデビュー前のアイドル、通称「リトル」の男の子たちの物語にされたんですね。
小説の中では「余命」という言葉を使ったんですが、入所してから一〇年以内にデビューできなければ、自動的にリトルから卒業になる。明確な期限がある中でアイドルに青春を捧げる男の子たちだからこそ、いろいろな感情が描けるんじゃないかなと思いました。その一方で、これは男女に限らずなんですが、アイドルの持続可能性についても書いてみたかったんです。ちょうどその頃、人気グループのメンバーが適応障害で活動休止するというニュースが出たり、「睡眠時間三時間で頑張っています」みたいな発言をされている人を見かけて、それって大丈夫なのかな、ずっと活動を続けられるのかなと考えてしまったんですよね。アイドルの持続可能性の問題って、ひるがえって、自分自身の立場の問題でもあるなと思ったんです。
―― 作家としての持続可能性、つまり、自分はずっと小説を書き続けられるのか……と。
はい。私は最初の本(『ブラザーズ・ブラジャー』)を出せたのは二〇二一年なんですが、断ったら次がなくなるんじゃないかという怖さから、原稿依頼をどんどん引き受けてしまった時期がありました。パンクしかけたんです。でも、読者さんから、お手紙だったりイベントでお会いした時に「無理をしないでくださいね。長く読めるのが一番幸せですから」と言われ、仕事の仕方を改めました。読者さんが私に言ってくださったことって、私自身がアイドルに願っていることと同じなんですよ。ここ数年で自分自身が「推される」側に回ったからこそ、実感を込めて書けた小説だったんじゃないかと思っています。
全員、応援したくなるキャラにしたかった
―― 一編ごとに主人公=語り手が代わる、全六編の連作形式が採用されています。第一編「サマーマジック」の主人公は、入所五年目の
世間一般に思われているアイドルのお手本って、「全力」だと思うんですね。でも、アイドル自身が思うアイドル像は一人一人違うし、ステージへの取り組み方も違うはず。ステージ上でぶっ倒れてもいいという人もいれば、公演に穴を空けないことが何よりも大事だと考えて、「省エネ」と言われるような力の抜き方をあえてしている人もいると思うんです。一編目の主人公は、その後のお話にもしっかり関わってくる狂言回し的な役割にしたいという思いもあり、少し俯瞰的な目線を持ったキャラクターにしてみました。
―― 透は、ファンの熱狂もクールに見ていますよね。中学時代の友人との会話が印象的でした。女子にモテるだろうと言われて、「モテないよ」「ウソだ。キャーキャー言われてんじゃん」「あれはファン。モテるにカウントしない」と。
そのセリフは、男性アイドルの逃げ方あるあるなんですよ。モテるよねと聞かれたら、「ファンにはいっぱい好きだと言ってもらいますけど、学校では全然ですよ、僕なんか」と言ってかわす。それをもうちょっと身内用のぶっちゃけに練り直してセリフにしたんですが、オタクが読んだら「あるある!」って首がもげるほど頷くと思います(笑)。
―― そんな透が気にかかっているのは、尊敬するリトルの先輩・
小説として面白いことをしたかったんです。第一段階までは結構匂わせているし予測もつくと思うんですが、もう一段階上のところは驚いていただけるんじゃないかなと思います。一編ごとに主人公を代えると決めていたので、最初に六人分のプロフィールをかっちり作って、キャラのイメージを固めておいたのもよかったのかもしれません。
―― キャラ作りは大変でしたか?
わりとすんなり、でした。男性アイドルソングって、歌割りにメンバーのキャラクター性が反映されてることが多いんですね。例えば、元気づけるような歌詞のパートは元気系の子が歌う、とか。そう言えばあの曲ではここの歌詞をこういうキャラの子が歌っていたな……とつらつら思いを巡らせているうちに、いつの間にか六人分のキャラクターができあがっていました(笑)。
―― みんなそれぞれに欠けている部分がある。だからこそ、応援したくなると感じました。
弱い部分や人間臭い部分を書くことは大切にしました。全員、応援したくなるキャラにしたかったんです。頑張れって思ったり、幸せになってほしいと願ったり。私がアイドルに対して思っていることも、そこなんですよ。プライベートでは恋愛しようが結婚しようが何でもいいから、その人が思うような活動ができていたら、私はそれを見て勝手に幸せになりますから、と。
―― 他者に対して幸せになってほしいと思えるのって、すごく幸せですよね。
そうなんですよ。その感情を、読む人にも味わってもらいたいなと思ったんです。
アイドル誌の記事などでは読めない
見えない心の部分を言語化したかった
―― 第二編以降は、どのように主人公選びをしていかれたのでしょうか。第二編「夢のようには踊れない」はブスいじりに心を痛める入所四年目の〝もっちー〞こと
「省エネ」の透から始まったので、次の章では対照的というか、自分がアイドルであることやいつかデビューすることに対してがむしゃらな、もっちーを主人公にしました。その次の章では、もっちーと一番対照的なキャラクターである遥歌を主人公に。もっちーと遥歌は、「美醜」で対比になっています。アイドルの話を書くならば、容姿に関することは入れないとウソになるなと思ったんです。私は、六人の中であれば推しはもっちーなんですよ。実際にパフォーマンスを見たら好きになるのはもっちーだなと思うし、マイナスの面は持っていて誤解されがちなんだけれども、ベースとしてはいいやつ。六人の中で一番人間臭いと思います。
―― 作中世界では、一番人気は遥歌です。ファンの間では大人しいイイ子だと思われているけれども……。
一番ぶっ飛んでいるのはたぶん、遥歌です。アイドルとしては表に出せないことを、一番たくさん抱えている。
―― 〈プロ意識プロ意識言うなら、そっちだって、ファン意識高く保ってよって思う〉という言葉を飲み込んでいたりします。
あれは、オタクを刺しにいっていますね。自分自身を刺すぐらいの勢いで書きました。応援って、危うさもあるじゃないですか。本人は「あなたのためを思って言っているんです」というテンションで応援しているつもりなんだけど、はたから見たら、それはその人を傷つけていたりする。でも、そこってアイドル側からは言えないんですよね。思っていてもなかなか言えない。だからこそ、小説の中で書きました。アイドル誌の記事などでは読めない、見えない心の部分を言語化したかったんです。
―― そこは、小説家の出番ですよね。
「推し活」がブームになって久しいですが、推す側の人たちの言葉って溢れていると思うんです。でも、推される側って言葉を持ちにくいというか、言葉がまだまだ少ない。本当はこういうことを言いたいんだけど言えないんだろうなとか、このことでくすぶっているんだけどまだうまく言語化できていないんだろうな……と、インタビュー記事などを読んでいて匂う時があったんですよ。コンサートDVDなどを観ていて、現場で観ていた時は気づかなかったちょっとした仕草の中に、その人の気持ちが雄弁に語られているなと感じることがあったんです。何かに執着するとか嫉妬するとか、何かに疑問を抱くとか、アイドルが普段表に出せないような感情を想像して、どんどん言葉にしていく。それが作家としての私ができることだし、アイドルを題材にするならばやるべきことだと思っていました。
健やかにずっと輝ける
持続可能な光であってほしい
―― 佐原さんの小説は、読んでいると必ず「えっ、そっち行くの!?」という意外な展開が訪れるんですが、本作であれば入所六年目のプロフェッショナルアイドル・
連作短編なので、終盤にかけて何か大きな流れを作りたいなと思った時に、男性アイドルグループがYouTubeでやっていた企画を思い出したんです。自分が所属するグループ以外のメンバーを取り合って理想のグループを作る、というドラフト会議企画です。ファンの間でかなり人気の企画なんですよ。
―― エグい企画ですね!
それをもっとエグくしたら面白いかなと思い、こうなりました(笑)。エンターテインメント、フィクションとして、これをしたらキャラクターたちの関係性が大きく変わるいいギミックになるはずだ、と。
―― そのギミックがどんなものかは、実際に読んで確かめてほしいところです。第五編「掌中の星」の主人公は、入所五年目で芸能一家に生まれた
雑誌掲載のたびに毎回、熱烈なファンレターを送ってくださった読者さんがいるんですが、「蓮司がやばい」と言ってもらえて嬉しかったです。六人の中で、リアコ(=リアルに恋している、を意味する推し用語)枠は蓮司かな、と思っていたので(笑)。最後は若様にしようというのは、最初の段階から決めていました。第一編が「余命」の会話から始まっているので、最後は「余命」ぎりぎりの人を出したかったんです。
―― 蓮司と若様の関係性が素晴らしかったです。若様は、自分の才能に気づいていないんですよね。それを、蓮司はもどかしく思っている。
自分の才能に気づけていないというエピソードは、第一章の時からちらちらと入れていました。この小説のタイトルは『スターゲイザー』、星を見る(gaze=凝視する)人という意味です。そこにはファンが「スター」であるアイドルを見るという視線もあるし、コンサートでサイリウムを揺らす客席の星空っぽさに象徴される、アイドルから見たファンという視線もあります。それともう一つ、アイドルから見たアイドルという視線も重ね合わせているんです。本人は気づいてないんだけれども、すごく光っている部分を仲間がゲイズすることで、その人が変わっていく……そんな話にもなっているのかなと思います。
―― お互いを見つめ合ったからこそ、どんどんこの六人は強くなっていった。その先に、あのゴールテープが待っていたのは必然だったんですね。
私、小説を書いていて泣くことって今までなかったんですけど、最後はめっちゃ泣きながら書きました。それはたぶん、アイドルとしてステージに立っている彼らが感じたものと、作家としての自分が見たものとに通じ合うところがあったからで。イベントとかサイン会の時に、読者の方から「同じ時代に生まれてよかったです」と言ってもらって、自分はすごい仕事をしているんだなと驚いたし、感動したことがあるんですよね。その気持ちが、最後のシーンとリンクしていったんだと思うんです。書き終える時は、祈りに近いような感覚になったのをよく覚えています。アイドルオタクとしては、私の推している人たちが健やかにずっと輝ける、持続可能な光であってほしい、と。それと同時に、私自身も持続可能な光であり続けたい、と強く思いました。
―― 振り返ってみれば最初から最後まで光の話、でした。
光は、全体を貫くテーマでした。第一編で代替可能な光について書いて、第二編で隣に光が当たることに対するコンプレックスの話をやって、第三編はスポットライトが怖いという話で……。その後は、光にスターの比喩がだんだん絡んでくる。
―― 佐原ひかりという名前の作家が、「光」の話を書く。これって、何度もやれることではないですよね?
そうですね。一生に一度しか書けない、私にとって特別な作品になりました。

佐原ひかり
さはら・ひかり●作家。1992年兵庫県生まれ。
2017年、「ままならないきみに」でコバルト短編小説新人賞受賞。19年、「きみのゆくえに愛を手を」で氷室冴子青春文学賞大賞受賞。21年、同作を改題・加筆修正の上で書き下ろしを加えた『ブラザーズ・ブラジャー』でデビュー。他の著書に『ペーパー・リリイ』『人間みたいに生きている』『鳥と港』がある。